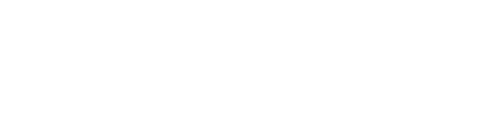2. お祭りと歌 その2
前ページ(お祭りと歌 その1)で紹介する御囃子の一部(2番歌詞)の中の「きたきた 浜町の白ギツネ」に関する昔話を紹介します。チョロリを漢字表記しますと「潮浪里」です。
チョロリ稲荷の白ぎつね
むかしむかしのこと
八代と潮来の境にチョロリ稲荷というのがあった。このお稲荷さんはもうずっと昔からそこにまつられていた。
いまではにぎやかな町並みの中に立派にまつられているが、そのころは村はずれの淋し森の中にあった。そのころ、潮来の里には、遊郭もたち並び、港は出船入船でにぎわっていて、夜もたくさんの人が集まってきていた。遠く八代の村にも、毎夜お祭のような笛太鼓の音がかすかにきこえてきたりしたものだった。八代の村の中には、その音曲に引き寄せられるかのように、潮来の夜の町へ遊びに行くものもいた。
八代の利三郎と静六は、村でもなだいのほうとう者で、ひまさえあれば夜の潮来へと通っていた。その日も利三郎と静六は潮来の料理屋ですっからかんになるまでいつづけ、金がないとなると、金の切れ目は縁の切れ目とばかり、ポイとおもてへほうりなげられてしまった。
利三郎と静六は悪たいをつき、ほろ酔い気分も手伝って、夜中なのに村へ帰ることにした。八代と潮来をつなぐ道は稲荷の森を通っていた。この稲荷の森は、昼でもうすぐらく、家もなく淋しいところだった。利三郎と静六は稲荷の森のあたりに来ると、酔いもさめてきて、月あかりにみえる森をみると、なんとなく夜中に帰ってきたことを後悔しはじめ、酔いざめの寒さとともに、足のひざ小僧がカタカタするようになってきた。
「利、利三郎、な、なんだかおっかねえな」
「や、やい、せ、静六、お、おめえ、おっかながっていんのが」
「そ、そうでねえが、お、おいはぎでも出んでねえかと思ってよ」
「ばか、おいはぎが出たって、とられるものなんかあんめえよ」
「そ、そしたら、ゆ、ゆうれいでも・・・」
「ゆ、ゆうれい、ひ、ひとをおどかすようなこと言うでねえ」
二人はゾゾッとしてきて、おっかなびっくり歩いていた。
「ヒェー」
二人は飛び上がらんばかりにおどろいた。
「もし、お二人さん、ああ、びっくりした。なにをおどろいているんですよ」
「な、なんだ女でねえけ」
「な、なんだ、おめえは」
「まあ、よかった。私も心細くて怖くってこまっていたんですよ。私は芸者のおこんと言うんだけど、後生だから潮来まで送っておくれよ」
利三郎と静六は、ふるえながらも、この女がゆうれいでもなく、おいはぎでもなかったのでほっとしながらも、そのおこんさんを送っていくことになった。
おこんさんを送ることにして、いまきた道を引き返しはじめたが、行けども行けども森の中。やっと一軒家のあかりがみえてきた。どうやらこうやらその家にたどりつくと、「どうもすみませんでしたねえ。どうぞあがってお茶でもいっぱいやっていって下さいな」といわれて二人は、もう一度稲荷の森を帰るのは心細いし、これ幸いとばかり、おこんさんの家にあがりこんだ。
こんなところに家があったっけかな、と思ってはみたものの、お茶がお酒にかわり、一杯二杯とやっているうちに、いい気持ちになってしまった。いつものくせで飲めやうたえの大さわぎ「お風呂をどうぞ」と言うんで「飲みながらいっぱいやっぺやあ」とお風呂につかりながら酒盛りをしていた。
突然、冷たい水をぶっかけられた利三郎と静六。はっとしてまわりを見廻すと、まわりには見覚えのある大勢の村人が笑いころげていた。太陽はもう南の空にのぼり、早春のどろ田の中で、二人は腰までつかりながら、いまのいままでさわいでいたのだ。
「あれれ、あの女は」
「おこんさん」
と泣きべそをかきながら呼ぶと、集まっていた人びとはどっと笑いころげる。
「利さぶ、せえ、お前らなにしてんだ」
「きつねにだまされたんだっぺえ」
わあっと笑いころげる人びとの間をほうほうの態でにげだした二人。
もう二度と夜の潮来に遊びに行くこともなく、二人はまじめに働きだしたそうだ。
村人たちは、この稲荷にあぶらげをささげ、化かさないようにお願いするようになった。
きたきた 潮来の白ぎつね お客をだまして 泥をこね
いつまでもいつまでも語りぐさになったとのことだ。
※本文にある「八代(やしろ)の村」は「八代村」です。昭和30年(1955年)に香澄村と合併し牛堀町となりました。現在の上戸地区、島須地区です。牛堀町は平成13年に潮来町と合併し潮来市の一部となりました。
※チョロリ(潮浪里)稲荷神社は、昭和35年国道51号の開通に合わせて、稲荷山の一角から上戸川公民館の隣に移転しました。
(出典:大塚野区のあゆみ)