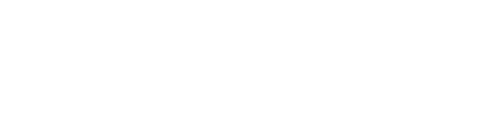3. 素鵞熊野神社の御祭神 -牛頭天王様から須佐之男命へ-
素鵞熊野神社は、明治10年(1877)に素鵞社と熊野社が合名して素鵞熊野神社と改称しました。素鵞社の前は、文治4年(1185)から、天保14年(1843)までの約660年間は牛頭天王社です。その後、天保14年12月に出されました水戸藩の神仏分離の令により、牛頭天王社は素鵞社と改称しました。この時、御祭神も仏教の牛頭天王から神道の須佐之男命に改めています。現在、日本の牛頭天王社の宗社は、京都市東山区祇園町に鎮座します八坂神社です。昔は祇園社、感神院、祇園天神、牛頭天王社などとも呼ばれ、疫病退散や邪気祓いに効験があるとされていましたが、明治初年(1868年)に神仏分離令により、仏教色を廃して御祭神をも牛頭天王から素戔嗚尊に改め、古来の地名から現在の八坂神社と改称しています。同時に全国の祇園社や牛頭天王社も社名を八坂神社に、祭神を素戔嗚尊に統一しています。
御祭神を牛頭天王から素戔嗚尊に改め、と書きましたが、牛頭天王という仏様が素戔嗚尊という神様と習合したと考えることが出来ます。八坂神社の御祭神素戔嗚尊はイコール牛頭天王です。全国に素戔嗚尊を祀る神社は約9千社ほどありますが、その多くは明治の神仏分離令まで基本的には牛頭天王社と呼ばれ「天王さん」と親しまれていました。私達の護持する牛頭天王社が、素鵞社に改称されられても、私たちは歴史に倣い天王さん、天王様、天王様の御神幸と親しんでいます。ここに歴史に培われてきた言葉のすばらしさがあります。