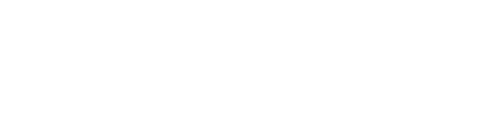5. 潮来節と祭りポスター
潮来祇園祭禮のポスターには,「潮来節(いたこぶし)」と書かれた歌謡が左上側にあります。
この歌謡は甚句形式の「7.7.7.5」の音数律に従う26文字の定型詩です。通説は,『潮来節は,香取・鹿島参詣で賑わった常陸国の水郷潮来を起点とし,江戸の遊里で流行をみせ,その後全国的に伝播した流行歌謡であった。流行の始発時期は宝暦年間(1751~1764)頃で,元歌は「いたこ出島の 真菰の中に あやめ咲くとは しほらしや」と考えられる』と述べています。基本は男女の情愛を歌うものです。「7.7.7.5」の26文字でひとつの歌謡となり,現在2千曲余りが記録されています。祭禮ポスターに250年前から続く歌謡が掲載される例は,潮来祇園祭禮以外にその例を見出すことは,甚だ困難です。
最近では,伝統の歌謡ばかりではなく,新しい潮来節も掲載されています。
伝統の潮来節
- 恋に焦がれて鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が身を焦がす(平成26年)
- 縁と時節を待とは云えど 時節ばかりか片時も(平成28年)
新しい潮来節
- 水面鏡に天空そびえ 祭り知らせる大幟(平成25年)
- 潮来出島のあやめの街で 街衆総出の賑やかし(平成29年)