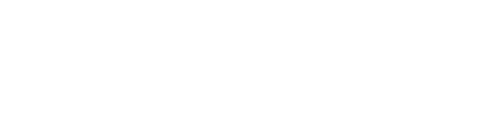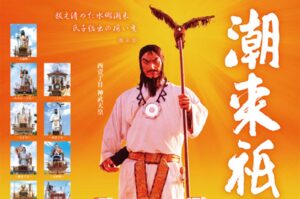6. 拍子木「チャキ」
若連頭のみが持つ拍子木があります。仲間内では「チャキ」とも呼んでいます。若連頭はこの拍子木を打ち合わせる回数で山車の運行、止まる、出発、回れ等を指示します。拍子木は美しい紐で結ばれています。若連頭のみが持つ拍子木の大きさは1辺約6cm角×長さ約50cmです。主に樫の木や桜の木で製作されています。歌舞伎でも拍子木が使用されます。歌舞伎の拍子木は4面の内1面が蒲鉾型の曲面となっています。2つの曲面と曲面を打ち合わせて音を出しています。曲面と曲面が打ち合わさる部分は事実上「点」となる部分です。ここが打ち合わさり音が出ます。点の部分から音が出るため、その音は、とても清んだ気持ち良い高音です。波が広がるように広がります。若連頭が打ち合わせる拍子木の音は、面と面が打ち合わさり音が出ます。その音はややつぶれた様な高音です。この拍子木を歌舞伎用語を真似て「ツケ」と言う方もいます。拍子木を打ち合わせることを「柝が入る」とも表現します。「柝」は拍子木のことです。歌舞伎の用語です。
※「チャキ」について
拍子木をチャキと呼ぶ例は全国にあります。何故、チャキと言うのでしょうか。チャキとは「拍子木の音を表わす語」(日本国語大辞典)です。拍子木の発する音が、その物の名前に転化したと考えることが出来る例です。今日、チャキは拍子木の俗語となっています。その物が発する音が、その物の呼び名になる例は、身近な所では幼児語に見られます。ぶーぶーは自動車です。ごろごろ様は雷様です。(擬音語・擬態語辞典 角川書店)チャリンコは自転車です。チャリンは自転車のベルの音です。